|
|
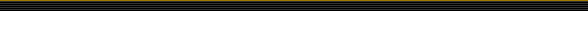 |
 |
 |
電卓(でんたく)は下から0、1、2、3・・・。電話機は上から1、2、3・・・で最後に0。どちらも0から9の数字を使うのに、ならびがほぼ反対なのはなぜでしょうか? |
 |
 |
 電卓のボタン配列は、「計算をするのに、最も多く使う0が手前にあった方が使いやすい」という理由から、下から0、1、2、3・・・のならびになっています。ちなみに、電卓のボタン配列は、最初から全部同じだったわけではありません。カシオが最初につくった「14-A型」は、現在(げんざい)の電卓のボタン配列と同じでしたが、その6年後にイギリスの会社がつくった世界初の電卓は、各けたごと10個(こ)ずつのボタンが、たてにずらりとならんだ「フルキー式」というならび方でした。しばらくは「フルキー式」の電卓もつくられていましたが、けたに関係なく、下から0、1、2、3・・とならぶ方が計算しやすいと感じる人が多くなり「フルキー式」の電卓は姿(すがた)を消していきました。 電卓のボタン配列は、「計算をするのに、最も多く使う0が手前にあった方が使いやすい」という理由から、下から0、1、2、3・・・のならびになっています。ちなみに、電卓のボタン配列は、最初から全部同じだったわけではありません。カシオが最初につくった「14-A型」は、現在(げんざい)の電卓のボタン配列と同じでしたが、その6年後にイギリスの会社がつくった世界初の電卓は、各けたごと10個(こ)ずつのボタンが、たてにずらりとならんだ「フルキー式」というならび方でした。しばらくは「フルキー式」の電卓もつくられていましたが、けたに関係なく、下から0、1、2、3・・とならぶ方が計算しやすいと感じる人が多くなり「フルキー式」の電卓は姿(すがた)を消していきました。 |
 |
 |
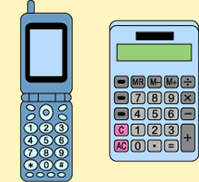 一方、電話のボタン配列は、ITU-T(国際電気通信連合の電気通信標準化部門・こくさいでんきつうしんれんごうのでんきつうしんひょうじゅんかぶもん)によるもので、上から1、2、3・・・とならぶのは、そのならびが自然だからという理由のようです。電卓(でんたく)が登場したころの電話機はダイヤル式で、数字のボタンはまだ付いていませんでした。日本で最初に0から9の10個(こ)のボタンをおす電話機が登場したのは1969年のこと。当初はおしボタン電話機とよばれていて、「プッシュホン」というよび名は翌年(よくねん)の公募(こうぼ)によってつけられました。 一方、電話のボタン配列は、ITU-T(国際電気通信連合の電気通信標準化部門・こくさいでんきつうしんれんごうのでんきつうしんひょうじゅんかぶもん)によるもので、上から1、2、3・・・とならぶのは、そのならびが自然だからという理由のようです。電卓(でんたく)が登場したころの電話機はダイヤル式で、数字のボタンはまだ付いていませんでした。日本で最初に0から9の10個(こ)のボタンをおす電話機が登場したのは1969年のこと。当初はおしボタン電話機とよばれていて、「プッシュホン」というよび名は翌年(よくねん)の公募(こうぼ)によってつけられました。 |
 |
 |
電卓と電話機が、ちがったボタンのならびになってしまったのは、使いやすいかたちがちがうからなのですね。 |
 |
|
 |
 |
|