|
|
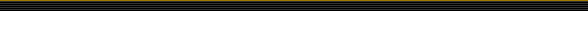 |
 |
 原始時代、人間は指を使って数を数えていました。両手両足を使っても、一人で数えられるのは20まで。大きな数を数えるときには、人数が必要でした。やがて「もっとかんたんに数を数えられる方法はないか?」と考え、洞(どう)くつの壁(かべ)などに絵をかき、しるしを刻(きざ)んで数を数えるようになります。そして次は計算した数字を動かせるように、木切れや小石などの「モノ」を地面にならべて数えるようになりました。 原始時代、人間は指を使って数を数えていました。両手両足を使っても、一人で数えられるのは20まで。大きな数を数えるときには、人数が必要でした。やがて「もっとかんたんに数を数えられる方法はないか?」と考え、洞(どう)くつの壁(かべ)などに絵をかき、しるしを刻(きざ)んで数を数えるようになります。そして次は計算した数字を動かせるように、木切れや小石などの「モノ」を地面にならべて数えるようになりました。
やがて、モノとお金の交換(こうかん)がはじまると、もっと便利に計算するための機具が必要になってきました。 |
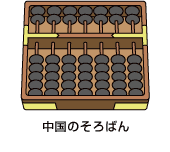 そして、計算機のはじまりと言われている「アバカス」が古代ギリシャで誕生(たんじょう)しました。テーブルにひかれた線の上で、カルクリとよばれる小石を動かすことで、たし算や引き算をすることができました。 そして、計算機のはじまりと言われている「アバカス」が古代ギリシャで誕生(たんじょう)しました。テーブルにひかれた線の上で、カルクリとよばれる小石を動かすことで、たし算や引き算をすることができました。
その後、中国や日本などのアジアでは、木の枠(わく)に棒(ぼう)をたてにならべ、珠(たま)がそれにそって上下する「そろばん」が使われるようになりました。たし算や引き算はもちろん、九九ができれば、かけ算やわり算もすることができました。
|
| またヨーロッパでは「ネピアの棒(ぼう)」という計算機具も登場しました。これはそれぞれの面に数が書かれている四角い棒を組み合わせて、かけ算やわり算をすることができました。この考えは、17世紀には計算尺(けいさんじゃく)に引きつがれました。そして、その計算尺とそろばんは、計算機が普及(ふきゅう)するまで、多くの地域(ちいき)で長い間使われていました。 |
|
このように古くから人と計算は深い関係にあり、生活がゆたかになるにつれて、正確(せいかく)さや便利さをもとめて、次々(つぎつぎ)に新しい計算機具をつくるようになったのです。 |
|
 |
 |
|